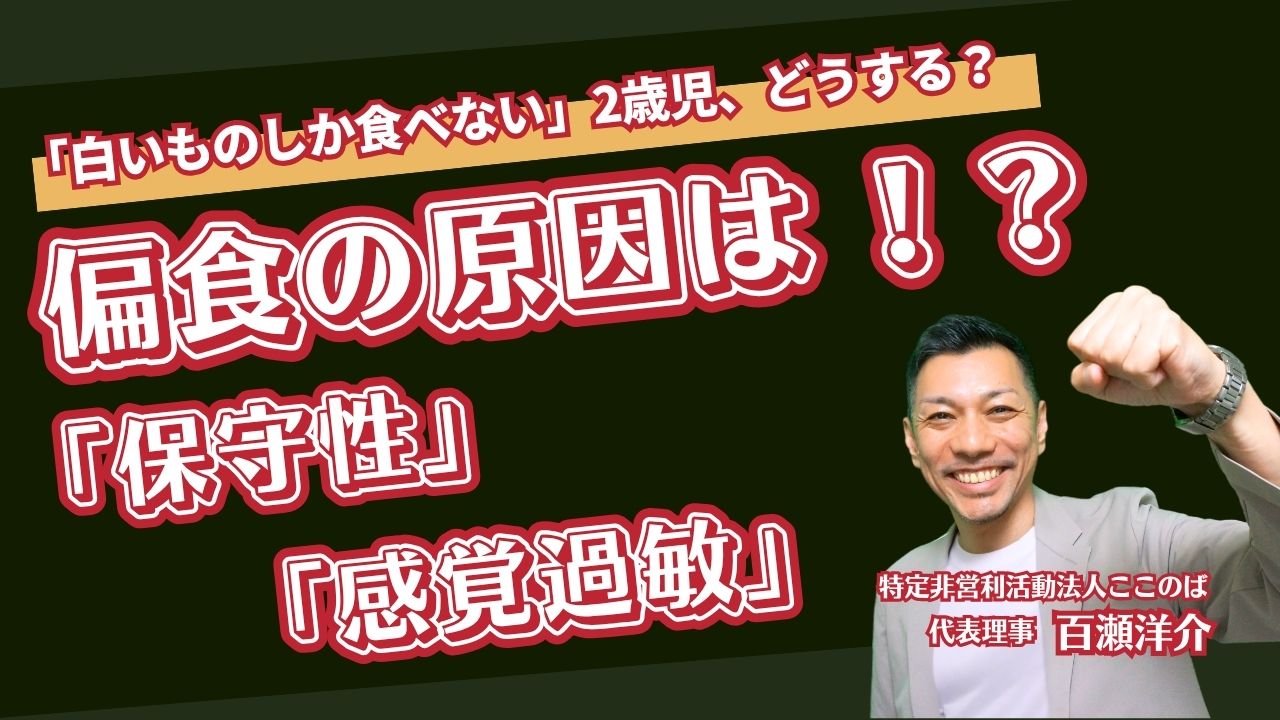本記事では、極端な偏食の子どもへの対応を整理します。
療育や保育の研修については、療育と保育の学びの会(児童発達支援事業のための研修)をご確認ください。
オンライン所要30分・無料相談はこちら
はじめに
2歳児の「白いものしか食べない」偏食にどう対応する? 「2歳児クラスの男の子が、ご飯やうどんなどの白いものしか食べません。どのように対応すれば良いでしょうか?」というご質問に対し、こちらの動画では専門家がその原因と対応策について解説しています。
極端な偏食の主な原因は2つ
お子さんの極端な偏食には、主に2つのキーワードとなる原因が考えられます。
1. 「いつものものが安心」と感じる保守性
保守性とは、「いつものものが安心」という心理状態によるものです。海外旅行中に何も情報がない中で飲食店を選ぶ際に、普段からよく知っているマクドナルドを選びたくなるような感覚です。この傾向が強いお子さんは、普段と違うものに対して強いストレスを感じやすい傾向があります。特に、自閉症傾向の強いお子さんには、このような「いつものものが良い」という傾向が強く見られることがあります。
2. 味や食感への反応が強い感覚の過敏さ
感覚の過敏さとは、文字通り、食べ物の味や食感(触覚)に対して感覚が過敏であることです。特定の味がとても変に感じられたり、特定の食感が生理的に受け付けない、といった具体的な例が挙げられます。
偏食の原因は複数:保守性と感覚過敏の相互作用
経験的に見て、お子さんの極端な偏食の原因は、これら「保守性」と「感覚の過敏さ」の両方が混在しているケースが多いとされています。どちらか一方の割合が多いケースもありますが、多くの場合、これらは相互に作用します。例えば、感覚が過敏なお子さんは、その感じやすさゆえに警戒心が強くなりやすく、それが知らないものへのストレス耐性を弱めることにも繋がり得ます。
2歳児の偏食への具体的な対応策
保守性への対応:ストレスなく少しずつ変化を加える
保守性の強いお子さんには、お子さんがストレスを感じないレベルで**「少しずつ変化を加えていく」**ことが有効です。例えば、ご飯の中に細かく刻んだ野菜を、お子さんが分かりにくいように混ぜてみるなどの工夫が考えられます。ただし、この方法は食事を提供する側の負担が大きいため、無理のない範囲で行うことが重要です。また、非常に敏感なお子さんの中には、わずかな変化でも全く受け付けないケースもあるため、「できれば」という範囲で試すのが良いでしょう。
感覚の過敏さへの対応:焦らず長い目で見守る
感覚の過敏さについては、年齢を重ねるにつれて緩和される傾向にあります。動画の専門家は、小学校に上がるなど、もう少し大きくなると、偏食全体が少しずつ緩和されていくことが多いと述べています。そのため、今は食べられなくても、長い目で見ていく姿勢が大切です。
最重要ポイント:種類よりも量を優先して栄養確保
偏食への対応において、最も重要なのは**「種類」よりも「量」を優先する**という考え方です。栄養が全く取れず、栄養失調になることが最も避けるべき最悪のパターンです。仮に、うどんやご飯といった特定の白いものしか食べなくても、十分な量を食べられているのであれば、それを良いと考えるべきです。無理に食べさせようとすると、お子さんが食事自体を嫌いになってしまい、結果的に何も食べなくなるリスクがあります。お子さんが「楽しく」食べられるものを、量をしっかり食べられるようなスタンスで取り組むことをお勧めします。
オンライン所要30分・無料相談はこちら