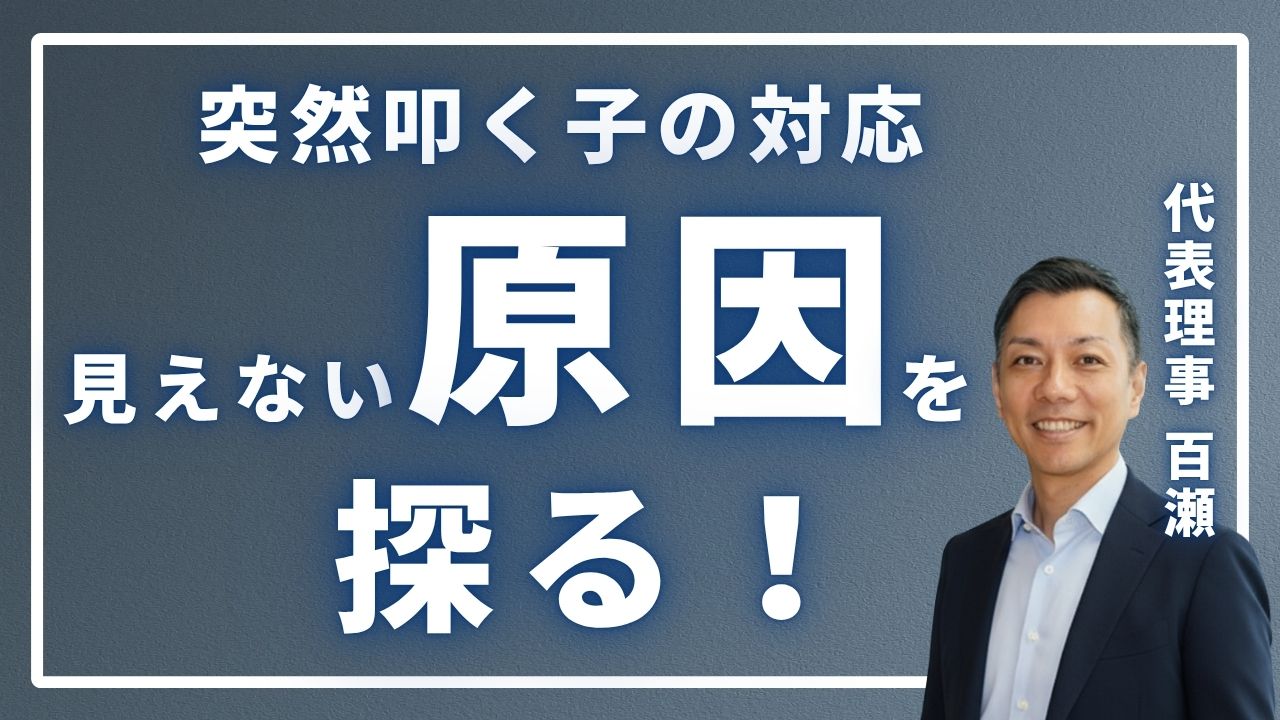本記事では、突然お友だちを叩く子どもへの対応を整理します。
療育や保育の研修については、療育と保育の学びの会(児童発達支援事業のための研修)をご確認ください。
オンライン所要30分・無料相談はこちら
突然お友だちを叩いてしまう行動の背景にあるもの
保育や療育の現場で、「なぜ叩いているのか分からない」状況に遭遇することは少なくありません。例えば、ブロック遊びに没頭しているお子様(M君のケース)が、突然近くのお友だちを叩いてしまう、といった行動です。
一見すると何の理由もなく起こったように見えるこれらの行動ですが、実はその背景には必ず原因やきっかけが存在しています。何の理由もなしに叩くということはほとんどないと考えてください。対応を考えるためには、この「必ず原因がある」という大前提を念頭に置き、その原因を探ることが重要です。
原因には、おもちゃを取られた場合のように分かりやすいものもあれば、周りから見ていて分かりにくいものもあります。特に、発達の特性に関連する分かりにくい原因を想定できる「仮説の引き出し」を多く持っておくことが、適切な対応につながります。
「分かりにくい原因」として考えられる仮説(感覚過敏や情報処理の困難さ)
ここでは、一見して「なぜ?」と思ってしまう行動の裏に隠れている、いくつかの原因の仮説をご紹介します。
仮説1:感覚的な過敏さによる「防衛行動」
お友だちが近くに寄ってきた際、触覚的な過敏さを持つお子様は、接近に対して強い警戒心や不安を感じる場合があります。その結果、「あっち行け」というメッセージを伝える防衛行動として、バンと叩いたり押したりするケースが考えられます。
仮説2:情報処理・調整の難しさによる「精神的な動揺」
感覚の調整機能がうまく働かないお子様は、情報処理に困難を抱えることがあります。
• 没頭中の突然の情報: おもちゃに没頭して集中している最中に、突然お友だちが視界に入ってくるなど、視覚的・聴覚的な情報が急に入ってくることによって、精神的に動揺してしまう可能性があります。これは、私たち大人でも、何かに集中している時に突然暗くなったり、何かがパッと視界に入ってくると動揺するのと同じ状況です。
• 聴覚的な過敏さ: 私たちが気にしないような音(例えば、車やパトカー、救急車の音)や、園内であれば他のお子さんの泣き声などに、過剰に反応してしまうケースもあります。私たちがその音が行動の引き金になったことに気づかない場合でも、お子様にとっては強いストレスや動揺の原因となっていることがあります。
• 情報のフィルター機能の困難さ: 本来、人間には、多くの情報(車の音、先生が喋っている音など)の中から必要なものを選び出し、集中して聞くためのフィルター機能(調整機能)があります。この調整機能がうまく働かないと、どの情報を仕入れればいいのか分からなくなり、情報過多となり混乱することがあります。没頭している最中に情報が入りきらなくなるケースもあれば、情報が多すぎることによってパニックに近づき、行動として出てしまう可能性も考えられます。
仮説3:思い込みによる「予防的な行動」
お友だちがただ近くに寄ってきただけなのに、「おもちゃを取られるのではないか」という思い込みが先行し、「取るなよ」という意図で押したり叩いたりするケースも考えられます。これは、過去の経験や不安から、予防的に行動を起こしている状態です。
仮説4:複数の原因の積み重ね(複合的な要因)
単一の原因ではなく、いくつかの要因が積み重なって行動となって表れるケースもあります。
• 気持ち的な負荷: 体調不良でしんどい状態にある、またはその日、保護者の方や保育者から制止されたり怒られたりして、気持ち的にモヤモヤしたりイライラしている状況(ストレスが積み重なっている状態)があります。
• 引き金となるきっかけ: このような気持ち的な負荷がある状態に、お友だちが近づいてきた、などの**小さなきっかけ(引き金)**が加わることで、行動として叩くことが出てしまうことがあります。
同じきっかけ(お友だちが近づく)があっても、ストレスの積み重ねがなければ行動が出ないというケースも存在するため、原因の特定をさらに難しくしています。しかし、日頃の様子から「前日の行事で疲れていなかったか」「午睡がうまくできていなかったのではないか」など、深く原因を推察することで、複合的な要因を把握しやすくなります。
対応へのヒント:日頃から仮説の「引き出し」を増やす
お子様の行動に対応する上で重要なのは、日頃から、分かりにくい原因(特に感覚的な要因)を含めた仮説の「引き出し」を多く作っておくことです。
引き出しが多ければ、「もしかしたら、音に反応したのかもしれない」「視覚的な情報が急に入って動揺したのかもしれない」というように、様々な可能性を洗い出すことができ、適切な対応策を見つける助けになります。
書籍や動画などを通じて、お子様が示す多様な行動の背景にある可能性について理解を深めることが、日々の療育・保育の現場で役立ちます。
オンライン所要30分・無料相談はこちら