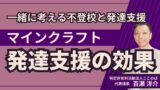まず、本記事では教育版マインクラフトが発達障害・ASDの子どもに与える影響を、国内外の研究からわかりやすく整理します。次に、実践に移す際の視点も短くまとめます。なお、実際の支援内容はマインクラフト×発達障害のオンライン個別支援で詳しくご確認いただけます。
オンライン無料説明会・所要30分/教育版アカウントは当方で発行

GLOBAL GAME
発達特性のあるお子さま向けに、マインクラフト(教育版)を活用したオンライン個別療育を提供しています。楽しさを入口に、関わり・自信を少しずつ取り戻します。
はじめに
発達障害や自閉スペクトラム症(ASD)を持つ子ども・青年に対し、サンドボックスゲーム「マインクラフト (Minecraft)」が社会性発達などに寄与するとの報告が増えています。米国ではASD児者向けの非公式サーバー「Autcraft」の事例が論文報告され、日本でも信州大学などで教育・医療分野の研究が進められています。本稿では、社会性(対人コミュニケーション)向上を中心に、学習支援、認知発達、感情調整といった効果について、国内外の学術研究を概観します。
社会性・コミュニケーション能力の向上
オンライン共同プレイによる社会的つながり
マインクラフトは自由度の高い協働プレイを通じ、対人交流のプラットフォームとなり得ます。代表例がASD児者のためのオンラインコミュニティ「Autcraft」で、参加者(自閉症の子どもと家族)はマインクラフト内で安全に交流し、協力し合うコミュニティを形成しています。直接的な対面交流が苦手なASD当事者でも、Minecraft上では自分のペースで社会的目標を達成し、ポジティブな対人経験を積むことができると報告されています。実験的な検証は限られますが、Autcraftの民族誌的研究からは、同サーバー内で協働や社会化、コミュニティ形成が活発に促進されたことが示唆されています。このようにMinecraftは、孤立しがちな発達障害児者に仲間と繋がる場を提供しうる一方、現実の対面交流を完全に代替するものではなく、あくまで交流機会を補助・促進する手段と位置付けられています。
協働タスクを用いたソーシャルスキルトレーニング:
Minecraftの協力プレイを構造化して社会技能訓練に活用する試みも報告されています。MacCormackらはASD青年を対象に、レゴ療法を応用した「Minecraftクラブ」を実践しました。このプログラムでは3人1組の自閉症の若者グループが、マインクラフト内で「みんなで水族館を作る」等の共同目標に取り組み、建築役・デザイン役・監督役といったローテーション役割を担います。参加者は自分の得意分野を活かしつつ協力することで、協調的コミュニケーション能力の向上が図られました。インタビューと観察による質的評価では、Minecraftという動機づけの高い自然な環境の中で、参加者が「自分が得意なことを活かして他者と関わる」経験を積むことで対人スキルを伸ばしたことが示唆されています。この結果、ASDの若者がオンライン上で主体的かつ効果的に社会活動に参加し、有意義な対人関係を築けることが示されたと報告されています。実際、本クラブでは保護者やファシリテーターからも、参加者同士の協力・交流が円滑に進み自信を深める様子が観察されています。
日本における実践例
日本でも特別支援教育の現場でMinecraftを活用したコミュニケーション支援が報告されています。竜波周一らの実践研究では、特別支援学級の児童を対象にMinecraft: Education Editionを用いた協働学習を実施し、コミュニケーション能力と協働能力の向上を狙いました。この中では、「仲間の助けがなければ復活できない」ルール(ゲーム内でキャラクターが死亡した際、他のプレイヤーの支援でのみ復帰可能とする)や役割分担、共有の目標設定など、協力を促す世界の設定を工夫しています。その結果、児童たちに目覚ましい社会的進歩が見られ、他者と協力して課題を達成する姿勢が育まれたと報告されています。例えば、当初は他者との距離の取り方が苦手だった子どもが、ゲーム内では仲間のために自主的に農場を拡張し、「みんなの家にパンを置いたよ!」と仲間に声をかけるなど、自発的にチームを支える行動が見られるようになりました。この実践は、ルール設定や環境調整の重要性も強調しており、無秩序にMinecraftを遊ばせるだけでは効果は得られず、適切な仕掛けづくりが必要だと結論づけています。
対人不安の軽減と自信向上: グループでのMinecraft活動に参加することで、ASD児者の対人場面への不安が軽減し、自信が増すとの報告もあります。英国での科学テーマMinecraftクラブの評価では、参加した特別支援ニーズ児(小中学生)が「クラブ活動を楽しみ、科学知識が身についただけでなく、社会的コミュニケーション技能と自信が向上した」と子ども・保護者双方が回答しています。保護者からは「クラブは子どもが自信を持って友達を作り、コミュニケーション能力を伸ばす場になっている」との声が寄せられ、Minecraftという子どもにとって興味のある遊びを媒介にすることで、受容的でインクルーシブな交流環境が生まれていたと報告されています。同様に、日本のNPO法人の報告でも、Minecraftでの成功体験を積んだ子どもが自己肯定感を高め、現実の学校生活でも発言や登校に前向きな変化が見られたケースが紹介されています。
オンライン無料説明会・所要30分/教育版アカウントは当方で発行
学習支援・認知発達への効果
学習意欲と創造性の喚起
Minecraftの自由度と遊びの要素は、発達障害児者の学習意欲を高め、認知発達にも寄与すると期待されています。Riordan & Scarf (2017)は、本ゲームが問題解決力や創造力、計画力、粘り強さといった将来成功に必要なスキルを育む可能性を指摘しています。Minecraftではプレイヤーが未知の環境に対応し、試行錯誤しながら資源を集め目標を達成するため、論理的思考や空間認識の訓練につながります。実際、健常児を対象とした研究ですが、戦略系ゲーム(Minecraftに類似する要素を持つゲーム)のプレイが問題解決スキルの向上と学業成績の相関を示したとの報告や、Minecraftを授業に用いることで従来型授業より学習成果が向上したとの実験結果もあります。発達障害児においても、Minecraftの魅力により学習への没入度や集中力が高まりやすいことが指摘されており、教育版Minecraft(Minecraft: Education Edition)の活用が進んでいます。教育版では教師がクラス全体を管理しつつ協働課題を設定できるため、児童生徒が主体的・協働的に学べる教材として効果が報告されています。例えば特別支援学校での研究では、Minecraft上での協働学習を通じて協調性や課題解決能力に改善が見られ、教員らも通常の教科学習への良い波及効果を感じたとされています(この研究では先述の通り社会性訓練が主目的でしたが、結果的に子どもたちの探究心や計画力も刺激されたと考察されています)。
特別な興味の活用
発達障害児者はしばしば特定の物事への強い興味(「特異的興味」)を持ちますが、Minecraftはそうした興味を教育的文脈に結びつける媒介にもなります。上記の英国のMinecraftクラブでは、科学トピック(例えば恐竜の生態や宇宙など)を毎回テーマに掲げ、その知識をMinecraft内で再現・探究する課題を設定しました。子どもたちは好きなゲームを通じて学ぶことで集中力を発揮し、結果的に科学知識の定着や技術リテラシーの向上が報告されています。このようにMinecraftは発達障害児者の興味関心を学びに橋渡しするツールともなり得ます。自由な創造活動に没頭できる環境は、創造力の伸長や自己表現の機会にもつながり、認知面・情緒面での成長を支えるとの指摘があります。
感情調整・メンタルヘルスへの効果
不安・ストレスの軽減
MinecraftプレイがASD児者の不安やストレスを和らげる効果についても研究が進んでいます。Gehrickeら(2022)のランダム化比較試験では、6~12歳のASD児148名を対象に、8週間の運動プログラム群とレゴ/マインクラフト遊び群を比較しました。その結果、両群とも介入後に不安症状が有意に軽減し、8週時点で保護者評価・自己評価いずれにおいても不安スコアの改善が認められました(両群間差は統計的に有意でなく、運動と同程度にMinecraft等の遊びも効果があった)。すなわち、ASD児にとって好きなゲームに没頭すること自体が情緒の安定に寄与しうることが示唆されます。もっとも、この研究では介入終了8週後のフォローアップでは運動群のみで持続的な不安低減効果が確認され、遊び群では効果維持が見られなかったため、長期的には現実での体験を伴う介入との組み合わせが望ましいとも考察されています。
心理療法への応用
Minecraftの仮想世界は、ASD児者が現実では扱いづらい感情や記憶を表現・処理する場としても活用されています。Gerhardt & Smith (2020)は、幼少期にトラウマを抱えた11歳の自閉症男児に対し、トラウマフォーカスト認知行動療法の物語作り要素をMinecraft内で再現するケーススタディを報告しました。このゲーム療法では、子どもがMinecraft内で安心できる建物や風景を一緒に構築しながら自分の体験を語れるよう支援した結果、トラウマ症状の軽減や情緒面の安定が見られたとされています。著者らは「好きなゲームという安心基地を介すれば、言語や対人関係のハードルがあるASD児でも内面の物語を表現しやすくなる」とし、従来は困難だったASD児への心理療法にMinecraftを取り入れる意義を示唆しています。このケース以外にも、発達障害児者の支援に市販ゲームを療法的に活用する報告は増えており、レビュー研究でもMinecraftのような商用オフザシェルフゲームの精神療法的価値が注目されています。
自己調整と安心感
マインクラフトには感覚過敏への配慮や自己調整を助ける機能も備えられます。米国のAutcraftコミュニティ研究では、参加者がゲーム内に自分だけの「穏やかな庭」「暗い照明の落ち着ける部屋」など感覚刺激を調整できる空間を作り、過度なストレスを感じた際にそこでクールダウンする様子が観察されました。Ringlandらの研究では、Autcraftの管理者がMODを用いて虹色の感覚刺激ルームや音や光をオンオフできる暗室を実装し、プレイヤーが自分の感覚状態に応じて環境を選べる工夫が紹介されています。このようにMinecraftの仮想世界では、現実では難しい自己の感情・感覚のコントロールを練習でき、結果的に現実場面での落ち着きや自己肯定感向上につながる可能性があります。保護者同士のコミュニティ形成(例:Autcraft内の親フォーラム)により、子どもの情緒支援や情報交換が進む副次効果も報告されています。
オンライン無料説明会・所要30分/教育版アカウントは当方で発行
年齢層・Minecraftの種類・介入方法の違い
対象年齢と発達段階
調査された事例は主に小中学生から青年期に集中しています。小学生では学校教育や課外クラブでの利用例が多く、中高生では医療的支援(作業療法やソーシャルスキルトレーニング)での活用が見られます。成人ASDに対する直接の研究は少ないものの、一部にVR版Minecraftを用いたソーシャルスキル訓練の試みや、Autcraftのようなオンラインコミュニティへの参加による社会参加効果が示唆されています。年齢に応じて支援目標も異なり、小学生では協調学習や基本的対人スキルの習得、中高生では仲間作りや不登校・引きこもり傾向の改善、成人では就労準備やコミュニティ参加といった目的でMinecraftが位置付けられています。
使用されるMinecraftの種類
教育現場ではMinecraft: Education Edition(教育版)が多用されます。教育版は安全なクローズドな環境と教員向け管理機能(例:Classroom Modeで全員の位置や活動を監視)を備え、授業や療育でコントロールされた協働課題を実施するのに適しています。一方、Autcraftのようなコミュニティや一般の療育現場では通常版Minecraftに独自のMODやプラグインを導入して安全・安心な空間を構築する例もあります。例えばAutcraftサーバーではチャットのフィルタリングや荒らし対策MODが組み込まれ、ルール違反者を排除することでASD児が安心して遊べる環境を維持しています。家庭や個別療法では、市販のコンソール版やPC版Minecraftがそのまま用いられることもあり、子どもが慣れ親しんだプラットフォームで介入を行うことが重視されます。重要なのは、どのプラットフォームでも子どもにとって分かりやすく安心できる環境設定を行うことで、余計なストレスなく社会的・学習的課題に取り組めるようにすることです。
介入方法と集団構成
Minecraftを用いた介入は概ね次の形態に分類できます。(1) ピアサポート型オンラインコミュニティ: 参加者自身や有志の管理者が運営し、自由遊びを通じた自然な交流を図る(例:Autcraft)。(2) セラピスト/教師主導のグループ療法・クラブ: 専門家が目標やルールを設定し、少人数グループで課題に取り組む(例:MacCormackらのMinecraftクラブ、信州大学病院の集団作業療法、英国のMinecraft科学クラブ)。(3) 個別療法への組み込み: 1対1のカウンセリングや家庭療育にMinecraftを組み込み、子どもの興味を治療的に活用する(例:Gerhardt & Smithのケーススタディ)。どの形態でも、少人数での関わりがASD児には適しているとの指摘があります。大人数になると会話のテンポや場の空気を読む負担が増しコミュニケーションが難しくなるため、基本は1対1~1対3程度の枠組みで実施し、必要に応じてファシリテーターが仲介・支援することが望ましいとされています。実際、前述の研究の多くが2~4人程度の小グループで、専門スタッフまたは経験者(大学生ボランティア等)がサポート役に入る形を採っています。ファシリテーターは、子どもが躓いたときに提案をしたり、ルール順守や友達への配慮を促したりする役割を果たしつつ、主体的な遊び体験を損なわない程度の介入に留めることがポイントです。研究報告でも、子ども自身が主体的に選択・決定できる余地を残すこと(例:何を作るか、どのゲームモードで遊ぶかを自分で選ぶ)や、子どもを「教える側の専門家」役に立てて成功体験を積ませることが、社会性向上に効果的だったと述べられています。
おわりに
以上のように、Minecraftは発達障害・ASDを持つ子どもから大人まで、社会性の発達を中心に多面的な効果をもたらす可能性が示されています。対人関係面では、安全な仮想空間で仲間と協働・交流することでコミュニケーション技能や協調性、自信の向上が報告されました。学習面・認知面では、興味関心を引き出して問題解決力や創造性を育むツールとなり得ることが示唆されています。さらに、情緒面では不安の軽減や感情調整の場を提供し、心理的支えとなるケースも見られます。もっとも、多くの研究が示すように、こうした効果を最大化するには適切な環境設定と支援者の関与が重要です。ルール設計や参加支援の工夫次第で、単なるゲームが発達支援の強力なツールとなり得る一方、漫然と遊ぶだけでは十分な効果は得られないでしょう。今後、より厳密な対照実験や長期的影響の追跡を含め、Minecraftを活用した介入の汎用性と限界を検証する研究が求められます。ただ現時点でも、国内外の多様な事例が示す通り、Minecraftは発達障害児者の社会参加と成長を支える有望なプラットフォームであり、その可能性は教育・福祉・医療の現場でさらに活用されていくと期待されます。
実際のオンライン個別支援は「マインクラフト×発達障害のオンライン個別療育」ページでご案内しています。
オンライン無料説明会・所要30分/教育版アカウントは当方で発行

GLOBAL GAME
発達特性のあるお子さま向けに、マインクラフト(教育版)を活用したオンライン個別療育を提供しています。楽しさを入口に、関わり・自信を少しずつ取り戻します。
主な研究の比較一覧
以下に、本稿で取り上げた国内外の主な研究・実践例を表にまとめます。それぞれ対象や目的、Minecraftの利用形態、報告された効果を比較しています。
| 研究(著者・年) | 対象(年齢・診断) | Minecraft種類 | 介入方法(人数・ファシリテーター) | 目的・着目点 | 主な効果 |
| Ringlandら (2016) – Autcraftコミュニティ[3][4] | 自閉症の子ども・青年+家族(幅広い年齢) | 通常版(専用MODサーバー) | オンライン自主参加コミュニティ(多数、管理者あり) | 安全なオンライン交流の場提供 | 社会的交流の活性化、協働・コミュニティ意識の醸成[4](※効果の質的観察) |
| MacCormack & Freeman (2019) – Minecraftクラブ[6][7] | ASD青年(おそらく中高生) | 通常版(マルチプレイ) | 3人1組の小グループ×複数(ファシリテーター1-2名) | 協働作業によるソーシャルスキル訓練 | 役割分担による協力体験でコミュニケーション改善、協調行動の習得[7][8] |
| 竜波 (2021) – 特別支援学級実践[10][12] | 小学生・特別支援学級(ASD・ADHDなど) | 教育版 (Education Edition) | 学級内グループ学習(5-6名、教員が設定・進行) | 協働学習でコミュ力・協調性向上 | Minecraft内の独自ルールで協力を促進し、目覚ましい社会性の進歩[10](仲間と助け合う行動の出現[48]) |
| Hobbsら (2020) – Science Minecraft Club[24][14] | 特別支援教育が必要な児童・生徒(主に小中、英国) | 通常版(マルチプレイ) | 放課後クラブ(5〜10名程度、教師・ボランティアが指導) | 興味(ゲーム)を媒介に科学学習と社交促進 | 科学知識の習得、社会的スキルと自信の向上[14]、仲間づくり・包含的雰囲気の醸成[49] |
| Gerhardt & Smith (2020) – ケース報告[29] | 11歳自閉症男児+PTSD症状 | 通常版(シングルプレイ) | 個別療法(1対1、セラピストが誘導) | トラウマ治療へのMinecraft適用(ナラティブ療法) | ゲーム内で安心感を確保しつつトラウマ記憶を処理、不安・PTSD症状の軽減を確認[29] |
| Gehrickeら (2022) – RCT研究[26][27] | 6–12歳ASD児148名(米国) | 通常版(LEGO遊びと併用) | グループ活動(レゴ/マイクラ遊び群 vs 運動群、各~70名) | 遊びまたは運動による不安低減効果検証 | 8週間のMinecraft/LEGO活動で不安症状が有意に減少[26](運動群と同程度の効果); 遊び群はフォローアップで効果漸減[26] |
各研究で対象年齢や目的は様々ですが、総じてMinecraftを介した活動はASD児者の社会性発達にプラスの効果をもたらすことが示されています。それぞれの現場で工夫された介入デザイン(オンラインコミュニティ、構造化クラブ、教育利用、療法統合など)の違いにも留意する必要がありますが、表にまとめたような成果は今後の発達支援におけるMinecraft活用の有用性を裏付けるものと言えるでしょう。
参考文献: 本稿で引用した論文・資料の詳細は文中の引用【】内に示しました。それぞれ最新の研究動向を反映したものであり、さらなる情報については該当の文献を参照してください。
[1] [16] [21] [43] [44] [45] 〖マイクラ 発達支援の最前線〗発達障害・自閉症の社会性・自己肯定感を育むエビデンスと実践のコツ – COCONOVA
[2] 「マインクラフト」を用いた集団作業療法 – 長野県発達障がい情報・支援センター
[3] [4] [5] [17] [18] [19] [20] [22] [23] [42] Crafting minds and communities with Minecraft | F1000Research
[6] [8] [9] [40] (PDF) Part 2: The Virtual Environment Social Program for Youths With Autism Spectrum Disorder
[7] Therapeutically applied Minecraft groups with neurodivergent youth
[10] [11] [12] [13] [41] [48] 目次
https://kyouzai.jp/wp-content/uploads/2021/06/39_%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB.pdf[14] [15] [24] [49] ERIC – EJ1281092 – Shared Special Interest Play in a Specific Extra-Curricular Group Setting: A Minecraft Club for Children with Special Educational Needs, Educational & Child Psychology, 2020-Dec
オンライン無料説明会・所要30分/教育版アカウントは当方で発行

GLOBAL GAME
発達特性のあるお子さま向けに、マインクラフト(教育版)を活用したオンライン個別療育を提供しています。楽しさを入口に、関わり・自信を少しずつ取り戻します。