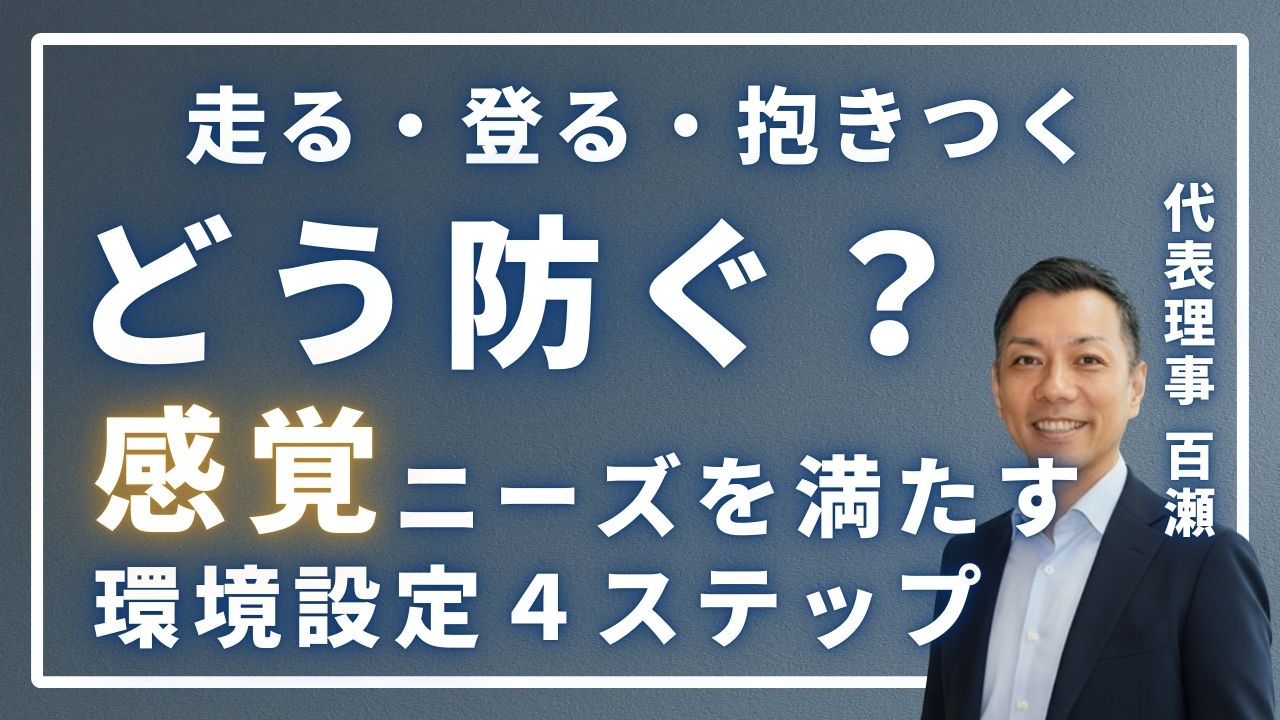療育や保育の実践研修については、療育と保育の学びの会(児童発達支援事業のための研修)をご確認ください。
オンライン所要30分・無料相談はこち
年中児の困った行動、その背景にある「感覚探求」の可能性
活動中に落ち着きがなく、走り回ったり、高いところにすぐ登ったり、さらには初対面の人にも抱きついてしまう年中クラスの男の子への対応に悩まれているケースがあります。どこまで見守り、どこから支援や制限をすべきか、線引きに迷うことは少なくありません。
こうした行動の背後には、一つの仮説として、お子さんの感覚が入りにくく、刺激を入れるために動き回っているという可能性があります。これは「感覚探求」とも呼ばれる行動です。
私たちは、例えば眠い時にストレッチをして体を伸ばし、刺激を入れて気持ちを覚醒させることがありますが、感覚が入りにくいお子さんは、その覚醒を求めて感覚を探求する行動を無意識に行っている場合があります。これが、むやみに走り回る、危険を顧みずに高いところに登る、見知らぬ人に抱きつくといった行動として現れ、刺激を入れている可能性があるのです。
※これはあくまで仮説の一つであり、絶対的な原因だと断定はできませんが、支援を考える上での重要な視点です。
感覚探求を満たし、集中できる環境を作る具体的な4つの支援策
感覚を求めやすいお子さんに対して、その行動を闇雲に「止めよう」とするのではなく、安全面と運用面に配慮しつつ、適切な刺激を与えて集中できる環境を作ってあげることが支援の大きな流れになります。
ここでは、具体的な支援策を4つご紹介します。
1. 「静」の活動の前に「動」の活動を取り入れる 椅子に座ってお絵かきやブロック遊びをするような「静の活動」(座って行う活動)の前に、外で走ったり飛んだりする「動の活動」(体を使った活動)を取り入れます。あらかじめ体をしっかり使って感覚を入れてあげることで、その後の静の活動への集中がしやすくなるという効果が期待できます。
2. 感触のあるものを活用する 泥や粘土、スライムなど、感触のあるものを握るのを好むお子さんの場合、それは感覚を入れる動作の一つになっています。これを制限するのではなく、無理なく握れるものを用意してあげるのがベストです。粘土やスライムは運用面で汚れが問題になることがあるため、握っても汚れたりしないグッズなど、運用面で無理なく使えるものを選んであげましょう。
3. 座位時に足裏に刺激を入れる環境設定 椅子に座る「静の活動」中に、足の裏に刺激を入れられるよう環境を整えるのも有効な選択肢です。例えば、足ツボマッサージ用のマットのようなものを、座る椅子の下に敷いてあげることで、座りながら感覚を適宜入れられる状態を作ってあげることができます。
4. 危険な場所や物を撤去する 環境設定として、やはり危険な場所や物はなるべく撤去しておくことが大切です。特に、高いところに登る行動が多い場合は、登れるような箇所を現実に撤去できるのであれば、事前にそうした危険にさらされない準備をしておくことが対策となります。
発達障害と感覚特性:知っておきたい基礎知識
感覚の特性は、他人からは分かりにくく、本人も他者と比べにくいため、見極めが難しいものです。支援者が基礎知識として持っておくと、仮説を立てる助けになります。
• ASD(自閉症スペクトラム)を持つお子さんのうち、80%以上が感覚の特性を持っていると言われています。ほとんどのお子さんが感覚の「苦手さ」や「特性」を持っているという視点を持つことで、より深くその子を理解することにつながります。
• 感覚特性は、一人の子どもの中でも複雑に混在します。例えば、同じ触覚であっても、「この部位は花瓶(感じやすい)だが、別の部位は感じにくい」といったように、感覚の発達がでこぼこしているのが特徴です。
感覚探求の行動は、お子さん自身が集中できる環境を求めているサインでもあります。適切な刺激を安全な方法で提供し、その子の特性に応じた環境を作ってあげましょう。
オンライン所要30分・無料相談はこち