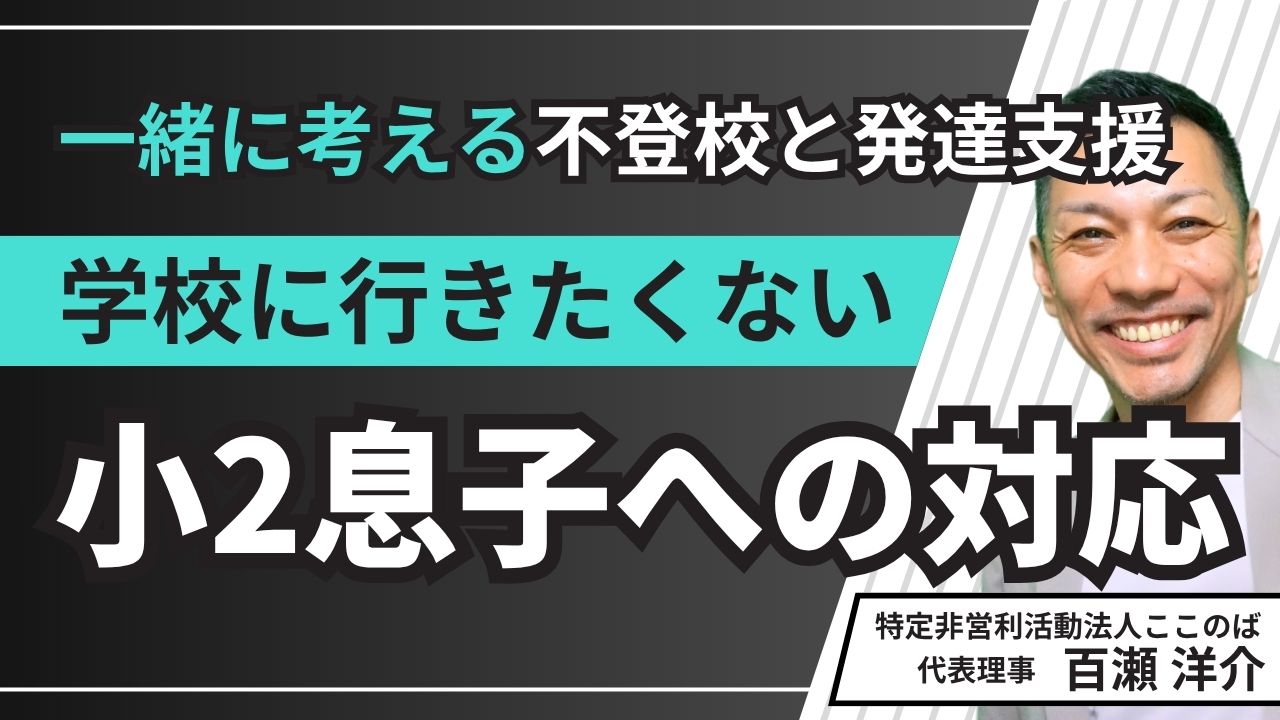本記事では、行き渋りをする子どもに対するかかわりを整理します。
実際の受け皿としては、オンラインのフリースクール(→詳しくは本校のご案内)もしくはマインクラフト×発達障害のオンライン個別支援をご確認ください。
オンライン活動説明会・所要30分・無料相談はこちら

SUPER SCHOOL
不登校や発達特性のある小中学生向けのオンラインフリースクールです。集団が苦手な子どもを対象に、マンツーマンの個別支援を中心に活動をします。
【小学2年生の行き渋り】「学校行きたくない」と言われたらどうする?専門家が解説
お子さんが突然「学校に行きたくない」と言い出したら、親としてはどうすれば良いのか、途方に暮れてしまいますよね。特に低学年の場合は、無理にでも行かせた方が良いのか、一度休ませたらそのまま行けなくなるのではないか、といった不安がつきまとうものです。
今回の記事では、YouTubeチャンネル「一緒に考える 不登校と発達支援」の動画「不登校についてのお悩み 行き渋り」の内容を基に、小学2年生の「学校に行きたくない」というSOSにどう向き合い、対応すべきかについて詳しく解説します。
小学2年生の息子さん「学校に行きたくない」…無理やり行かせるべき?
今回のお悩み相談は、小学2年生の息子さんが学校に行くのを渋り、「学校に行きたくない」と言われたケースです。お母さんは、一度休ませたら学校に行けなくなるのではないかという心配から、無理やり車で連れて行った経験もあるとのことです。
動画では、まず「画一的に学校を休ませるべきとは言えない」という前提が示されています。お子さんの学年、これまでの学校生活、学習面、家庭環境(保護者の方との関わり)などを考慮し、その子に合わせた対応が必要だからです。
しかし、今回の小学2年生のケースでは、「一旦休ませるべき」という結論に至っています。
なぜ低学年の行き渋りでは「休ませる」ことが重要なのか?
専門家は、小学2年生といった低学年で学校に行くのがしんどくなる状況は、「ご本人に相当な無理や負担がかかっている」「二次障害」を引き起こす心配があるため、思い切って休ませる対応が適切であると強調されています。
また、親から見ると「学校に行かなくなった」というのは問題の始まりのように感じられるかもしれませんが、お子さんからすると、それは「それまでの問題が蓄積された結果、初めて表面化した最終段階」であるという重要な視点も提供されています。お子さんにとっては、もうこれ以上無理だと示す「最後の手段」として、学校に行かないという選択肢を意思表示している段階なのです。
このため、この段階では無理に学校に行かせず、まず「休ませる」ことが最善の対応となります。
オンライン説明会。所要30分。無料相談はこちら
休ませた後の「回復期間」と「原因探求」
お子さんを休ませたら、次の日からすぐに学校に行けるようになるわけではありません。お子さんが心身ともに回復していくのを待つ期間を確保することが必要です。
そして、並行して、なぜ学校に行けなくなったのか、その「原因」を探っていくことも重要だとされています。ただし、小学2年生では、本人が原因をはっきりと言語化することは難しいため、焦らずじっくりと探ることが大切です。
原因を探るヒントとしては、以下のような点が挙げられています。
• 学校での様子を確認する:
◦ 担任の先生や、もし支援を受けている場合は支援の先生など、学校の様子を知る第三者から話を聞く。
• 具体的な側面から推察する:
◦ 友達との関わり: 学校で友達とどのように接しているか。
◦ 先生との関係: 先生との間で何か気になることはないか。
◦ 学習面:
▪ 授業を一定時間聞くのがしんどそうではないか。
▪ 板書を書き写すなどの「書く動作」をとても嫌がっていないか。
これらの情報を集め、お子さんの「苦手感」や「嫌がっていること」が浮き彫りになる中で、学校に行きたくなくなった原因が見えてくる可能性があるとのことです。
まとめ
お子さんの「学校に行きたくない」という言葉は、親への大切なSOSです。特に低学年の場合は、無理に登校させることがかえって心身の負担となり、二次障害のリスクを高める可能性があります。
まずは焦らずお子さんの心と体が回復するのを待ちながら、学校の先生とも連携し、お子さんにとって何が辛かったのか、その原因をゆっくりと探していくことが大切です。
この動画では、さらに詳しい解説がされています。お子さんの不登校や行き渋りに悩む保護者の方は、ぜひ動画をご覧になり、参考にしてください。
また、実際の受け皿としては、オンラインのフリースクール(→詳しくは本校のご案内)もしくはマインクラフト×発達障害のオンライン個別支援をご確認ください。
オンライン説明会。所要30分。無料相談はこちら

SUPER SCHOOL
不登校や発達特性のある小中学生向けのオンラインフリースクールです。集団が苦手な子どもを対象に、マンツーマンの個別支援を中心に活動をします。