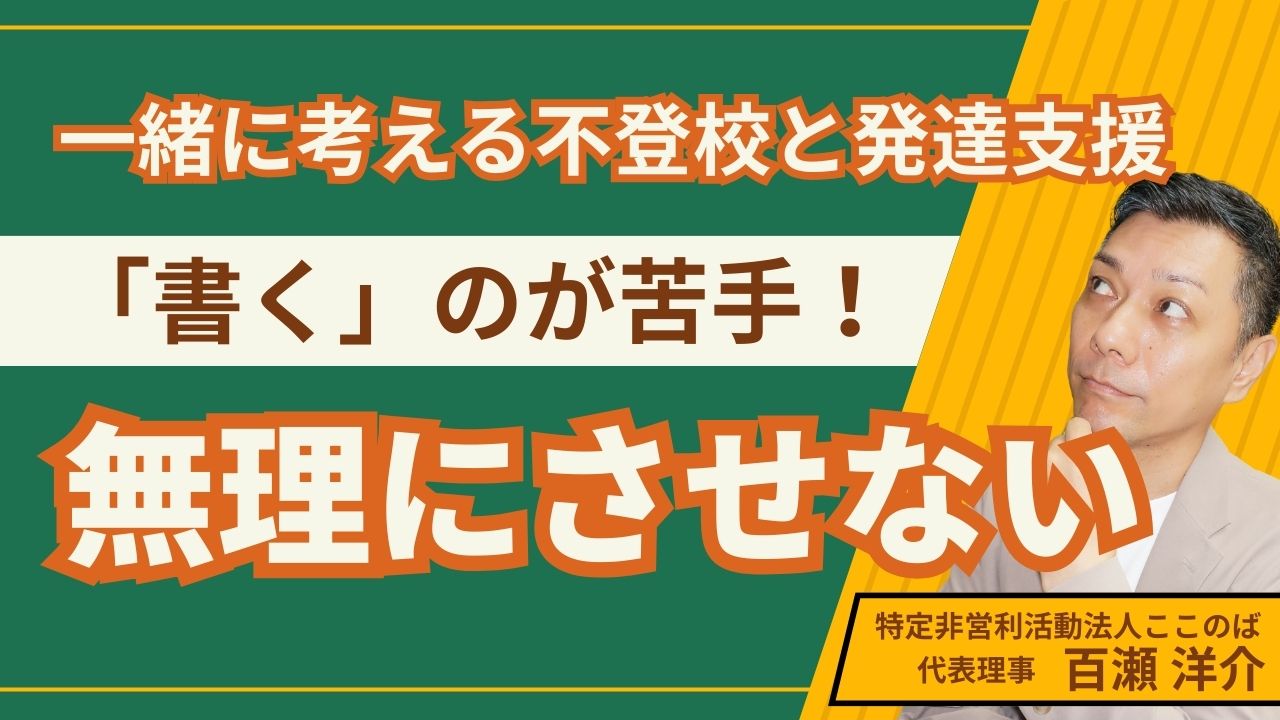本記事では、書くのが苦手な子どもに対するかかわりを整理します。
実際の受け皿としては、オンラインのフリースクール(→詳しくは本校のご案内)もしくはマインクラフト×発達障害のオンライン個別支援をご確認ください。
オンライン活動説明会・所要30分・無料相談はこちら

SUPER SCHOOL
不登校や発達特性のある小中学生向けのオンラインフリースクールです。集団が苦手な子どもを対象に、マンツーマンの個別支援を中心に活動をします。
書くことが苦手な小学3年生の息子さんへ:結論、無理にやらせないことが大切
「書くことが苦手」という小学3年生の息子さんをお持ちの保護者様からのご質問にお答えします。特に漢字は読めるのに、書くことが極端に苦手というお悩みですね。
結論から申し上げると、極端に苦手なことに関しては、無理にやらせない方が良いという考え方です。苦手な部分にはきちんと配慮し、代替手段を見つけることが重要になります。
オンライン活動説明会・所要30分・無料相談はこちら
「書くことの苦手」はどこから来るのか?WISCと処理速度の関連
そもそも、なぜ「書くこと」が苦手になるのでしょうか。これは推測ですが、**WISC(ウェクスラー式知能検査)**の結果に傾向が見られることがあります。例えば、視覚的な推論能力(見る能力)は高いのに、処理速度という能力に「凸凹(個人内差)」があるケースが挙げられます。
この処理速度の苦手さがあると、学校での**板書(ばんしょ)**が大きな負担になる傾向があります。板書は、先生が黒板に書いたものを見て、それを覚えながらノートに書き写すという、複数の処理を同時に行う必要があります。さらに、授業時間内という時間的な制約も加わるため、これが苦手意識につながり、結果的に「書くことが苦手」と感じるケースが多く見られます。
無理に書く練習をさせようとすると、学習全般に対して嫌な気持ちを抱いてしまう可能性もあるため、注意が必要です。
苦手さを乗り越えるための具体的な配慮と代替手段
書くことが極端に苦手な場合でも、様々な配慮や代替手段があります。
- デジタルツールの活用: 今ではパソコンやタブレットを使って文字をタイプすることができます。積極的にこれらのデバイスを活用することで、書くという行為のハードルを下げることができます。
- 「書けない」ことの本質を理解する:
- 多くの場合、指先の操作(運筆)そのものが苦手なのではなく、処理能力の問題から板書が苦手になっていると考えられます。
- 見本があればきちんと書き写せるお子さんも多いです。
- 一方で、漢字そのものを記憶し、思い出して書くことが苦手なケースも多くあります。
成長とともに変化する可能性と、大切なこと
現在小学3年生とのことですが、中学校に近づくにつれて、書くこと自体への抵抗感が減ってくることも期待されます。そのタイミングで適切な環境を整えてあげるのが良いでしょう。
重要なのは、お子さん自身の「苦手感」をきちんと把握し、その上で苦手なことに対しては無理にやらせない、または代替手段を身につけさせるといった工夫をしていくことです。この観点から活動を進めていくことをお勧めします。
実際の受け皿としては、オンラインのフリースクール(→詳しくは本校のご案内)もしくはマインクラフト×発達障害のオンライン個別支援をご確認ください。
オンライン活動説明会・所要30分・無料相談はこちら

SUPER SCHOOL
不登校や発達特性のある小中学生向けのオンラインフリースクールです。集団が苦手な子どもを対象に、マンツーマンの個別支援を中心に活動をします。