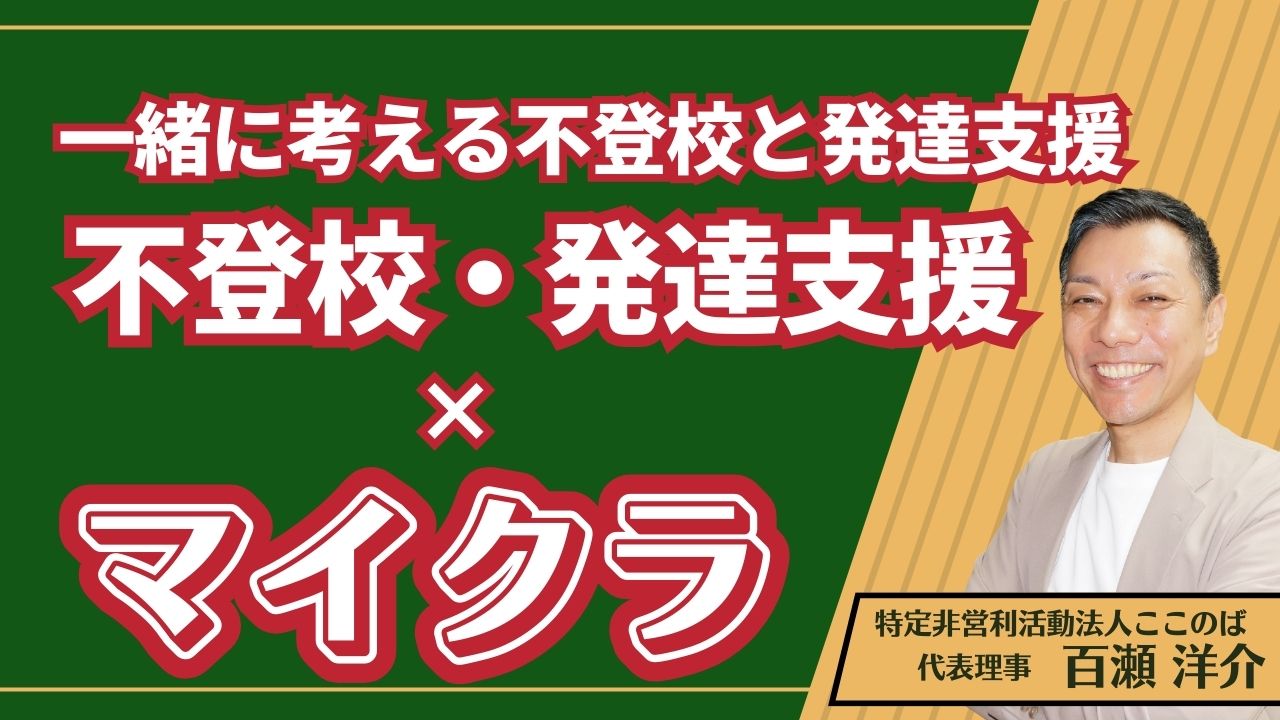皆さんは「マインクラフト(マイクラ)」をご存知でしょうか? 多くの方にとっては「ゲーム」という印象が強いかもしれませんが、近年ではプログラミングや英会話といった教育分野でも広く活用されています。そして今回、このマインクラフトが不登校支援や発達支援の現場で驚くべき効果を発揮している事例をご紹介します。
実際のオンライン個別支援は「マインクラフト×発達障害のオンライン個別療育」ページでご案内しています。
説明会を予約する(オンライン・無料・所要30分)

GLOBAL GAME
発達特性のあるお子さま向けに、マインクラフト(教育版)を活用したオンライン個別療育を提供しています。楽しさを入口に、関わり・自信を少しずつ取り戻します。
マインクラフトとは?その魅力と奥深さ
マイクラは発売から14年近く経つロングセラーゲームです。一般的なゲームとは異なり、明確な目的が設定されていません。プレイヤーは自分自身で目標や目的を設定し、自由に世界を創造していくことができます。この極めて高い自由度と汎用性が、マイクラ最大の魅力と言えるでしょう。
まるで「社会生活」!マイクラの世界で育まれる力
マイクラのワールドは、まさに私たちの社会生活そのものです。
• 衣食住の確保: お腹が空けば食料を確保し(狩猟・農業)、身を守るための住居を作る必要があります。
• 資源の収集と加工: 木を伐採し、石や鉱石を掘り、道具(斧やつるはし)や装備(防具)を製作します。これにより、さらに高度な資源(鉄やダイヤ)を採掘し、より安全で便利な生活を追求できます。
• 経済活動とコミュニティ: 村人との物々交換(取引)が可能になり、村や町を築くことで社会的な関わりが生まれます。
• 創造と発明: レッドストーン回路と呼ばれる電気信号のような仕組みを使い、自動ドアや大砲のような装置を作ることも可能です。
• これらの活動は、一人で進めることも、仲間と役割分担したり協力しながら進めることもできます。
あの「秘密基地」作りにも似たワクワク感
マイクラをプレイする感覚は、子どもの頃に友だちと協力して秘密基地を作ったり、Dr.STONEのように何もないところから知恵と素材を集めて便利なものを発明していく冒険感に似ています。協力しながら何かを作り上げるワクワク感や達成感は、マイクラが長く愛される理由の一つです。
説明会を予約する(オンライン・無料・所要30分)

GLOBAL GAME
発達特性のあるお子さま向けに、マインクラフト(教育版)を活用したオンライン個別療育を提供しています。楽しさを入口に、関わり・自信を少しずつ取り戻します。
発達障害・不登校支援におけるマインクラフト活用術のポイント
では、実際に不登校や発達障害を持つ子どもたちへの支援でマイクラを効果的に活用するためのポイントを見ていきましょう。
1. 個別対応(ワンオンワン)を基本に
◦ マイクラは複数人でのプレイも可能ですが、支援においては**スタッフ1名に対して子ども1名(最大でも2名まで)**が推奨されます。
◦ これにより、子どもが「できた!」という成功体験を積みやすく、自分のやりたいことが成功につながる環境を作りやすくなります。他者との関わりが苦手な子どもも多いため、1対1がより効果的です。
2. 目標設定と可視化をサポート
◦ マイクラは目標を自分で作るゲームだからこそ、支援者と子どもで「今日何をするか」「これからどう進めていくか」を話し合い、具体的にイメージを固めることが重要です。
◦ もし子どもが目標を言葉にするのが苦手な場合は、支援者側からいくつかの提案を行い、子どもの「やりたいこと」を引き出し、目標を「見える化」することが成功体験に繋がります。
3. 子どものコミュニケーション手段に合わせる
◦ コミュニケーションは大きく「受動的」と「能動的」に分けられます。
◦ 受動的コミュニケーション: 支援者からの問いかけに子どもが答える形(音声、テキスト)。いくつかの選択肢から選ばせるなども有効です。
◦ 能動的コミュニケーション: 子ども自身が発信する形。
▪ 「見て見て!」(注目と賛):作ったものを見せたりする、比較的引き出しやすいですが、自閉症傾向の強い子には難しい場合もあります。
▪ 「〇〇を取って」「〇〇して」(要求と依頼):必要なものを要求したり、手伝いを依頼したりする。
◦ 無理強いは禁物です。子どものコミュニケーションスタイルを見極め、それに合わせて関わることが、活動を嫌いにさせないために必要です。
4. 「できた!」の成功体験を最も重視する
◦ これこそが最も重要なポイントです。
◦ 小さなことでも「できた!」という達成感や成功体験は、子どもの自信に直結します。
◦ この成功体験を通じて、他者(支援者)と関わる楽しさを実感し、「他の子どもとも関わってみよう」という前向きな気持ちが育まれます。
◦ 集団での関わりが苦手で失敗経験が多い子どもにとって、成功体験を積み重ねることで、良い循環を生み出す支援が不可欠です。
まとめ
マインクラフトは、その自由度の高さと社会生活を模した構造、そして「秘密基地」のようなワクワク感を通じて、子どもたちの自発性や社会性を育む強力なツールとなります。特に、不登校や発達障害の支援においては、個別の関わり、適切な目標設定、柔軟なコミュニケーション、そして何よりも「成功体験」の積み重ねが、子どもたちの自己肯定感を高め、前向きな一歩を促す鍵となるでしょう
実際のオンライン個別支援は「マインクラフト×発達障害のオンライン個別療育」ページでご案内しています。
説明会を予約する(オンライン・無料・所要30分)

GLOBAL GAME
発達特性のあるお子さま向けに、マインクラフト(教育版)を活用したオンライン個別療育を提供しています。楽しさを入口に、関わり・自信を少しずつ取り戻します。