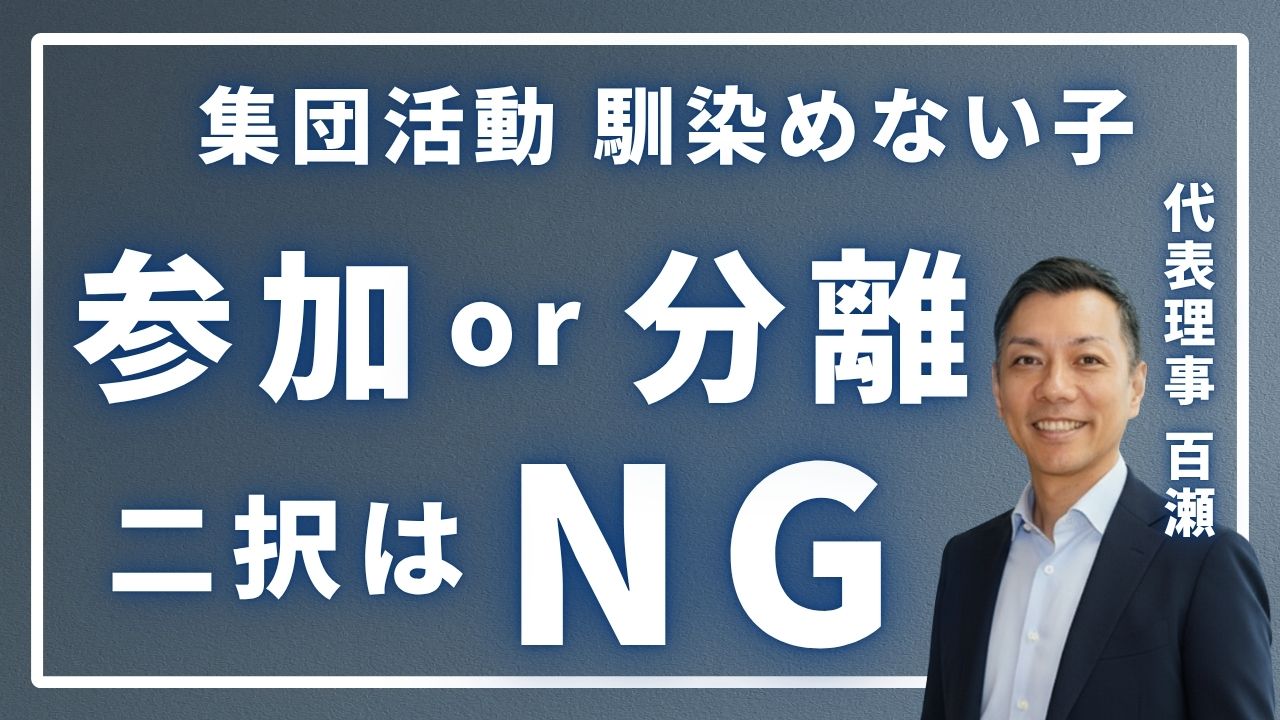本記事では、集団活動に馴染めない子どもへの対応を整理します。
療育や保育の研修については、療育と保育の学びの会(児童発達支援事業のための研修)をご確認ください。
オンライン所要30分・無料相談はこちら
1. はじめに:集団活動への対応の悩み
集団の活動にうまく馴染めない子どもへの対応は、多くの方が悩まれるケースです。集団に無理やり参加を促すべきか、それとも分離という形をとるべきか、対応に迷うことも少なくありません。
しかし、対応を考える上で最も重要な結論は、「集団に『参加させる』か『参加させない』かという2択で考えない」という点です。
具体的には、スモールステップという形で段階的に対応を考えていくことが重要となります。
2. 集団活動に馴染めない原因と背景
集団活動に馴染めない原因を探ることは、正論的なアプローチではありますが、馴染めない要素はいくつもあり、問題の切り分けや仮説立てには時間がかかり、専門家でも難しい作業です。保育という集団環境の中で、その原因特定を行うのは現実的に困難な場合が多いです。
ただし、比較的大きな割合を占める原因として、活動内容がお子さんの発達段階と比べて「難しすぎる」というケースが挙げられます。
• 活動の難しさによる回避行動: 活動が難しすぎると感じたり、活動の意図が理解できなかったりする場合、「やりたくない」という意思表示として、席を離れる(離席)といった回避行動につながることが多いです。
• 発達の個人差: 2歳児や年少時など、同じ学年の中でも発達の差が出やすい時期があり、例えば2歳になったばかりの子と、もうすぐ3歳になる子では、発達の開きが非常に大きい場合があります。
• 理解の遅れ: 例えば絵本の読み聞かせの際、発語やコミュニケーションが十分に取れる子がいる一方で、言葉の理解がこれからという子にとっては、話を聞いていてもなかなか楽しめないという状況が発生します。
このように、集団活動がお子さんの発達段階に合っていないことが、馴染めない原因の一つであるという視点を持つことが大切です。
3. 具体的な対応策:成功体験を積むスモールステップ
集団活動は、友だちと関わり、楽しい経験や充実感を味わう機会であり、その後の社会生活を送る上で大きな財産となります。そのため、基本的には集団活動に導いていくという方向性の中で、スモールステップによる対応を行います。
スモールステップの考え方とは、0か1かの対応ではなく、お子さんができるところの中間ステップを用意し、「できた」という成功体験を積み重ねていく方法論です。
3-1. スモールステップの具体例
集団活動の場での具体的な対応例を挙げます。
| 対応フェーズ | 具体的な活動例(絵本の時間など) | ポイント |
| 環境共有 | 絵本を読んでいる同じ空間(スペース)にいられることを認める。 | 別々の活動をしていても、同じ空間で過ごせていることを認めてあげる。 |
| 小さな承認 | 保育者の方を見るなど、小さな仕草があったら、「先生の方を見てくれたね」と認め声をかける。 | 小さな関わりを成功体験として積み重ねる。 |
| 活動のマッチング | その子に合わせた別の活動を個別で用意する。 | コーナー保育などを取り入れ、場所と活動を紐付け(例:このコーナーはブロック遊び)、子どもの主体性を引き出し、活動とのマッチングをしやすくする。 |
スモールステップで最も大事なのは、「できた」「褒められた」成功体験を積み上げることです。その成功体験を積み重ねられるような環境設定を工夫することが求められます。
3-2. 回避行動(離席など)への主体的な対応
集団活動が難しいと感じた際、お子さんがその場を離れてしまう(回避行動)ことはあります。これに対応するために、活動開始の際に、あらかじめ**「落ち着ける場所」**を用意しておくことは有効です。
ただし、ここで重要なのは、保育者の方が主体的にその落ち着ける場所に導いてあげることです。
• 子どもが「嫌だ」と感じて勝手に別室や目につく場所へ行って落ち着く、という形ではいけません。
• 保育者が「そろそろ難しいかな」と感じた時点で、「じゃあちょっと別室に行こうか」といった形で集団から離れる機会を作り、事前に用意していた落ち着けるもので主体的に落ち着く環境を作ってあげる必要があります。
保育者が主体的に環境を作ることで、「場所を変えて落ち着けたね」という形で子どもを認められる機会ができ、その経験が再現性を持ちやすくなります。子どもが主体的に回避する形になると、次に起こった際の予測が立てにくくなるため、保育者による主体的な対応が成功体験を積む上で不可欠です。
4. まとめ
集団活動への対応は、「参加させる/参加させない」の二者択一ではなく、スモールステップでお子さんに合わせた環境設定を行うことが求められます。
集団活動の中で、「楽しい」「よくできた」という成功体験を味わってもらうことが、その子の成長にとって最も大事な要素となります。
オンライン所要30分・無料相談はこちら