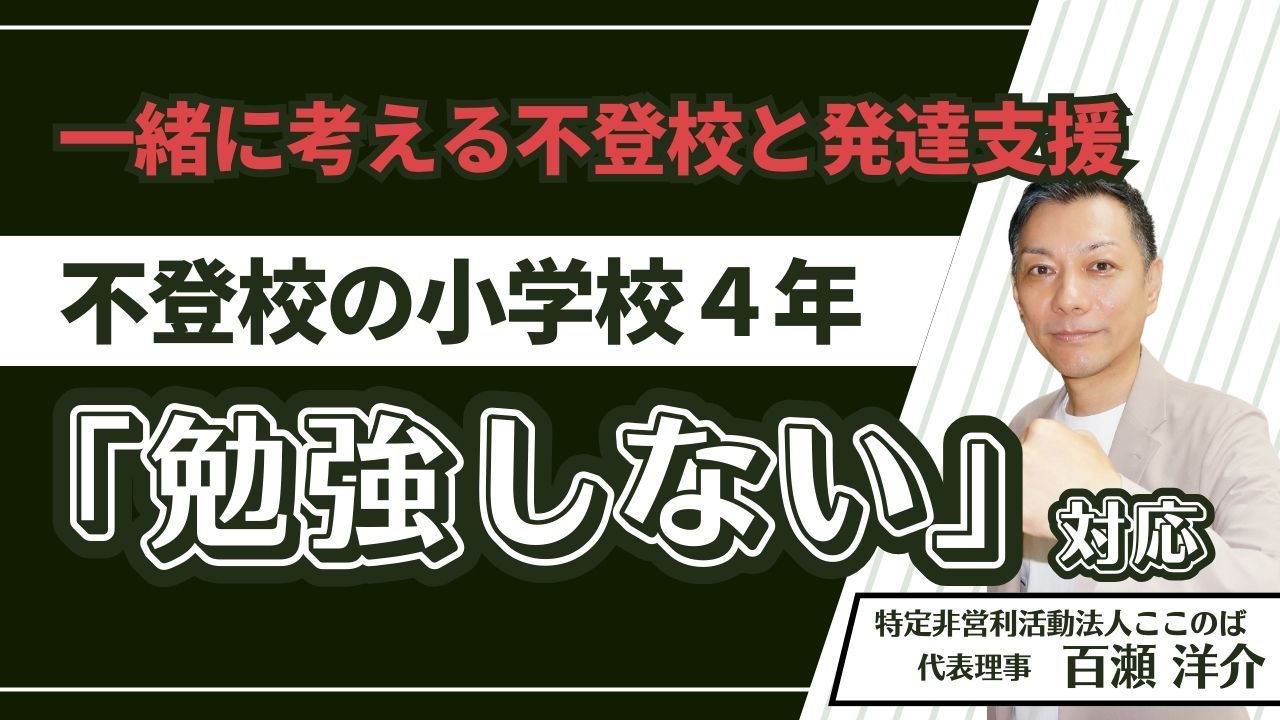本記事では、不登校で勉強をしない小学生について整理します。
実際の受け皿としては、オンラインのフリースクール(→詳しくは本校のご案内)もしくはマインクラフト×発達障害のオンライン個別支援をご確認ください。
オンライン活動説明会・所要30分・無料相談はこちら

SUPER SCHOOL
不登校や発達特性のある小中学生向けのオンラインフリースクールです。集団が苦手な子どもを対象に、マンツーマンの個別支援を中心に活動をします。
今回は、保護者の方からよくいただく「不登校で勉強を全くしない小学4年生の娘。一日中ゲームやYouTubeを視聴しており、親としてどうしたら良いか心配」という切実なご質問にお答えします。
お子さんが学校に行かず、学習にも取り組まない状況は、親御さんにとって大きな不安を伴うことと思います。私自身もそのお気持ちはよく分かります。
このブログ記事では、不登校のお子さんの学習面への向き合い方と、親ができる具体的な「環境作り」について、専門家の視点から詳しく解説します。
1. 学習面への対応:辛抱強く「芽生え」を「見守る」ことの重要性
まず、お子さんの学習面に関して、現時点でなかなか勉強に取り組めない、あるいは拒否感があるという状況の場合、辛抱強く本人の「芽生え」や「やる気」が出てくるのを見守るというスタンスが大切です。
なぜなら、本人がやる気のない中で無理に勉強させようとすると、相当な労力がかかるだけでなく、逆効果になる可能性もあるからです。また、そもそも学習面での苦手意識が、学校に行けなくなる要因になっているケースも少なくありません。
• 授業への集中困難: 例えば、学校の授業は40分から50分程度、一方的に聞くことが多いですが、ずっと集中して聞き続けるのが難しいお子さんもいます。注意が逸れてしまうことも多々あります。
• 板書(ばんしょ)の苦手さ: 黒板を見て書き写す「板書」が苦手だったり、書くこと自体が苦手だったりするケースもあります。こうしたことが苦痛となり、積み重なることで「学校に行くのがしんどい」と感じてしまうこともあるのです。
このような背景を考慮し、まずは焦らず見守ることが重要です。小学校高学年や中学校への思春期に向けて、「少し勉強をやってみようかな」という本人のやる気が芽生えてくるケースもよくあります。そのタイミングで、適切な学習環境を整えてあげれば良いのです。現時点では、まず「見守る」ことが必要となります。
2. 「やる気」の芽生えを促すための「環境作り」
ただ見守るだけでなく、本人の「やる気」の芽生えを促すような「環境作り」を並行して行う必要があります。具体的には以下の2点です。
(1)他者との関わりを持てる機会を作る 家族以外の方との接点、つまり「他者との関わり」を持つ機会を作ることが大切です。他者との関わりがない状況では、建設的な取り組みをしようという気持ちになりにくいものです。
現在では、様々な選択肢があります。
• リアルな居場所:
◦ フリースクール
◦ 教育支援センター
◦ 放課後等デイサービス こうした場所で、他の同世代のお子さんと交流する経験をしてみるのも良いでしょう。
• オンラインの選択肢:
◦ リアルな場所や集団が難しいお子さんには、オンラインフリースクールという選択肢もあります。オンラインで他者との関わりを作っていく経験ができます。
◦ 私たちの**「スーパー スクール」**では、集団が苦手なお子さんのために、オンラインで個別支援を行い、他者との関わりを通じて自信をつけてもらうようなサポートをしています。
このように、お子さんが無理なく関われるレベル感で、多様な選択肢の中から他者との接点を作っていくことが重要です。
(2)生活リズムを整える 学校に行っていないと、どうしても朝起きる時間が遅くなり、夜寝る時間も遅くなることで、昼夜逆転してしまうケースが多々見られます。
生活リズムが整っていないと、建設的な活動(特に学習面)に取り組もうという気持ちにはなりにくいものです。学校に行っていない中で生活リズムを整えるのは難しいことですが、以下のような工夫を試してみましょう。
• 他者との関わりの機会とセットにする: 例えば、決まった時間にフリースクールやオンライン支援に参加することで、自然と生活リズムが整うきっかけになります。
• 就寝時間の相談: お子さんと相談しながらでも良いので、ある一定の時間にはきちんと寝るようにするなど、就寝時間を整える取り組みを進めてみましょう。
まとめ
お子さんの学習面に関して、まず大切なのは**本人の「芽生え」や「やる気」が出てくるのを辛抱強く「見守る」**ことです。
そしてそれに並行して、「他者との関わり」や「生活リズムを整える」といった「環境作り」を進めることで、お子さんのやる気を育む土壌を醸成していくことが、私たち親ができる最初の一歩と言えるでしょう。
今回の情報が、不登校のお子さんを抱える保護者の方々の一助となれば幸いです。
実際の受け皿としては、オンラインのフリースクール(→詳しくは本校のご案内)もしくはマインクラフト×発達障害のオンライン個別支援をご確認ください。
オンライン活動説明会・所要30分・無料相談はこちら

SUPER SCHOOL
不登校や発達特性のある小中学生向けのオンラインフリースクールです。集団が苦手な子どもを対象に、マンツーマンの個別支援を中心に活動をします。