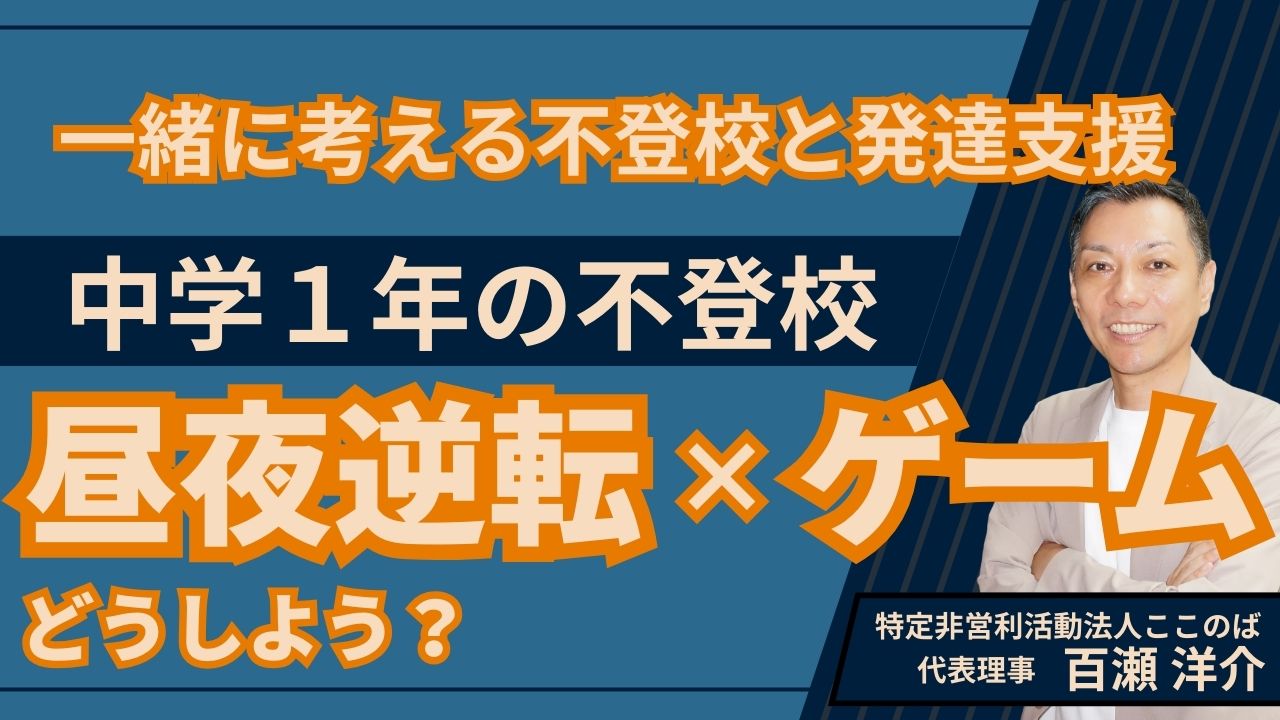本記事では、ゲームばかりをする子どもに対するかかわりを整理します。
実際の受け皿としては、オンラインのフリースクール(→詳しくは本校のご案内)もしくはマインクラフト×発達障害のオンライン個別支援をご確認ください。
オンライン活動説明会・所要30分・無料相談はこちら

SUPER SCHOOL
不登校や発達特性のある小中学生向けのオンラインフリースクールです。集団が苦手な子どもを対象に、マンツーマンの個別支援を中心に活動をします。
ゲームばかりの昼夜逆転、このままでいい?
「中学1年生の娘が不登校になり、朝までゲームをして昼夜逆転。ゲーム依存症ではないかと心配…このまま好きなようにゲームをさせておくべきでしょうか?」
これは、多くのお子さんが不登校や引きこもりになる中で、親御さんが直面する切実な悩みの一つです。今回の記事では、この問いに対し、専門家の見地から具体的な対応策を解説します。
「ゲーム依存症」は意外とレアケース?オンラインゲームの現実
まず、「ゲーム依存症」という言葉に過度に囚われる必要はありません。経験上、本当にゲーム依存症にまで至っているケースは全体の1割未満であり、比較的稀なことだと考えられています。
それよりも、多くの場合に見られるのは、オンラインゲームの特性による昼夜逆転です。オンラインゲームでは、ネット上の友人も夜に活動していることが多いため、自然と夜にゲームをして昼間寝るというサイクルになりがちなのです。
無理にゲームをやめさせると逆効果になる可能性
お子さんが不登校で学校というコミュニティにうまく馴染めない中で、オンラインゲームが唯一のコミュニティになっている可能性があります。この状況で無理にゲームを取り上げてしまうと、お子さんの活動の源を奪ってしまうことになりかねません。
また、無理な介入は親子関係をギクシャクさせてしまう可能性も高く、あまり推奨されません。大切なのは、頭ごなしに否定するのではなく、お子さんの現状を理解しようとすることです。
オンライン活動説明会・所要30分・無料相談はこちら
不登校の中学生、昼夜逆転・ゲーム問題への3つの具体的対応策
では、具体的に親としてどのような対応ができるのでしょうか?ここでは3つの視点から解説します。
1. 昼間に「楽しめる活動」を見つける
昼夜逆転のサイクルを改善するためには、まず昼間に活動できる場を作ることが重要です。
• 学校以外の選択肢: 現在では、フリースクール、放課後等デイサービス、さらにはオンラインのフリースクールなど、多種多様な選択肢があります。
• 「楽しさ」が最重要: 大切なのは、お子さんが「楽しめるかどうか」という観点です。集団が良いのか、個別が良いのか、リアルが良いのか、オンラインが良いのかなど、いくつか選択肢を提示し、見学や体験を通じて、お子さんが楽しめそうな場所を選ぶことが成功の鍵となります。
2. 就寝時間を早め、かつ一定にする
昼間の活動が見つかり、少しずつ生活リズムに変化の兆しが見えてきたら、次にお子さんと話し合って「寝る時間(就寝時間)」を決めていきましょう。
• 中学1年生に合わせた話し合い: 中学1年生という年齢を考慮し、一方的に決めるのではなく、お子さんとしっかり話し合いながら進めることが大切です。
• 「早め」かつ「一定」に: 「今日は11時、明日は9時」のようにバラバラになるよりも、「いつも夜10時頃にベッドに入る」といった形で、早めにかつ一定にすることを目指します。
• ゲーム時間へのルール設定: 話し合いの結果、「夜9時までにはゲームを終える」など、お互いが納得した形でゲームに関するルール作りも必要になる場合があります。
3. かかりつけ医に相談できる体制を整える
発達特性のあるお子さんの中には、ホルモン分泌がうまくいかず、寝ること自体が難しいケースも存在します。そのため、必要に応じてかかりつけ医に相談できるルートを作っておくことをおすすめします。
必ずしも服薬が必要というわけではありませんが、相談できる体制を整えておくことで、何かあったときに専門的なサポートを受けやすくなります。これは、長期的な視点で見ても非常に重要な準備となります。
まとめ
不登校の中学生が昼夜逆転でゲームに没頭している状況は、親御さんにとって大きな心配事です。しかし、無理にゲームをやめさせるのではなく、以下の3つのステップで焦らず対応していくことが大切です。
1. 昼間に「楽しめる活動」を見つける
2. 就寝時間を早め、かつ一定にする(お子さんとの話し合いが鍵)
3. かかりつけ医に相談できる体制を整える
お子さんとの良好な関係を保ちながら、それぞれの家庭に合ったペースで、これらの支援策を試してみてください。
実際の受け皿としては、オンラインのフリースクール(→詳しくは本校のご案内)もしくはマインクラフト×発達障害のオンライン個別支援をご確認ください。
オンライン活動説明会・所要30分・無料相談はこちら

SUPER SCHOOL
不登校や発達特性のある小中学生向けのオンラインフリースクールです。集団が苦手な子どもを対象に、マンツーマンの個別支援を中心に活動をします。