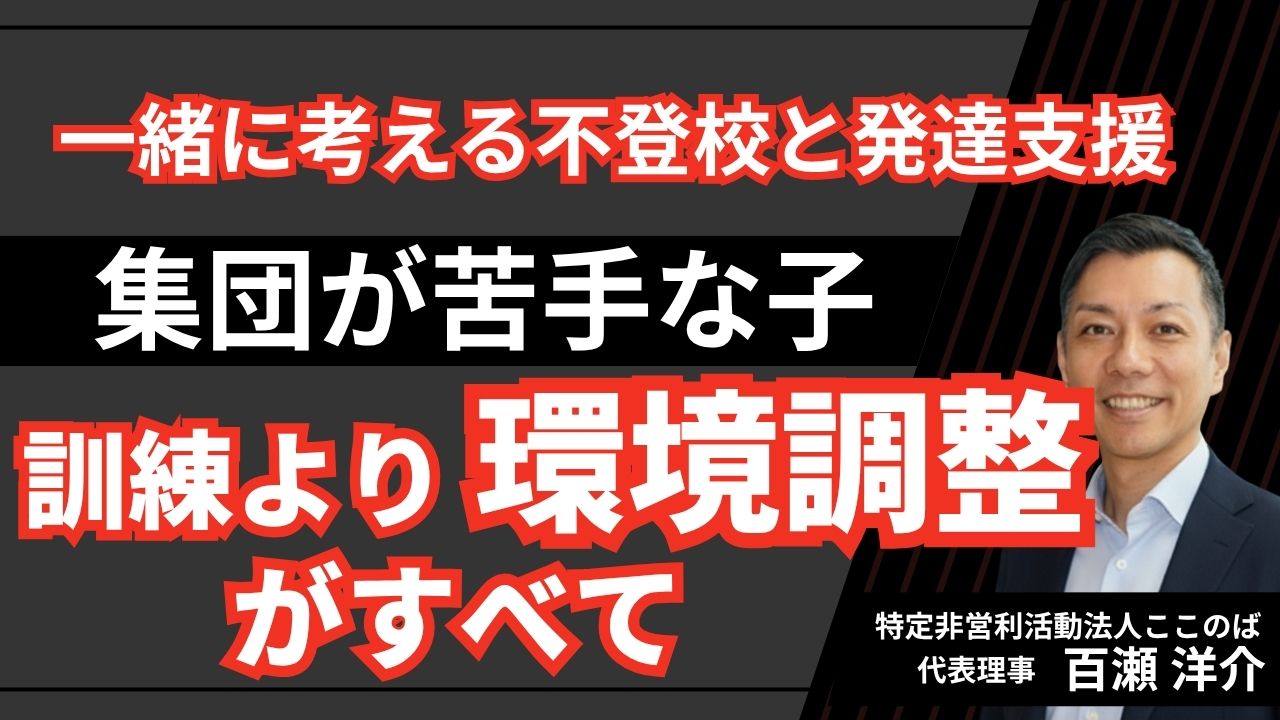本記事では、集団が苦手な子どもに対するかかわりを整理します。
実際の受け皿としては、オンラインのフリースクール(→詳しくは本校のご案内)もしくはマインクラフト×発達障害のオンライン個別支援をご確認ください。
オンライン活動説明会・所要30分・無料相談はこちら

SUPER SCHOOL
不登校や発達特性のある小中学生向けのオンラインフリースクールです。集団が苦手な子どもを対象に、マンツーマンの個別支援を中心に活動をします。
1. なぜ集団活動が苦手なのか?保護者からのよくある質問
「集団が苦手な子ども」の支援について、保護者の方からよくご質問をいただきます。特に、小学校に入学してから集団での活動に苦手意識を持ち、学校での活動に参加を渋ってしまうケースは少なくありません。
一方で、そうしたお子さんがマンツーマン(1対1)のプログラムや療育では機嫌よく活動できている、という点も重要なヒントとなります。
集団活動が苦手な背景には、主に二つの大きな要因が考えられます。これらの要因を理解し、適切な配慮を行うことが、子どもたちの心理的なハードルを下げるために大切です。
オンライン活動説明会・所要30分・無料相談はこちら
2. 集団が苦手な子どもに見られる二つの大きな要因
集団への苦手意識を引き起こす要因は、複合的である場合もありますが、ここでは特に重要とされる二つの要素について解説します。
2-1. 要因その1:言語の非流暢性(言葉が出にくい特性)
一つ目は「言語の非流暢性(ひりゅうちょうせい)」と呼ばれるものです。これは、言いたいことや考えていることは頭に浮かんでいるにもかかわらず、それが言葉として滑らかに出てこない状態を指します。
• DK反応(Don’t Know反応)との関連: WISCなどの検査で「DK反応」(分からない、知らない)として現れることがあります。考えがまとまっていないわけではなく、言葉としてうまく出力できないがゆえに、「分かりません」とすぐに反応してしまうケースです。
• 集団のテンポについていけない: 特に小学校2年生など、同世代の集団活動はテンポが速い傾向があります。自分の思考を言葉にするのに時間がかかる(非流暢性がある)と、周囲のスピードにうまくついていけず、結果として集団への苦手意識や抵抗感が出てきてしまいます。
• マンツーマンが有効な理由: マンツーマンの個別対応では、相手(大人)が子どもが言葉を出すのを待ってくれるため、スムーズに活動できることが多いと考えられます。
2-2. 要因その2:聴覚・視覚的な過敏さ(複合的な感覚のざつき)
二つ目は、感覚的な過敏さです。これは、聴覚、視覚、またはそれらの複合的な感覚が、集団の中で強く刺激されることで、集団生活が難しくなるケースです。
• 「ざつき」への反応: 集団の中には、様々な音や視覚的な動きが入り混じった「ざついた感じ」が存在します。こうした複合的な「ざつき」に対して、非常に敏感に感じやすいお子さんもいます。
• 集団を避ける理由: 過敏さがある場合、ざわついた集団の中にいること自体が大きな負担となり、結果として集団生活を避ける原因となります。
オンライン活動説明会・所要30分・無料相談はこちら
3. 集団生活の苦手さを軽減するための具体的な支援策
言語の非流暢性や感覚的な過敏さなど、これらの特性は「訓練によってすぐに改善するものではない」ため、まずは環境側で配慮してあげることが重要です。
3-1. 【最優先】人数を絞った活動環境の提供
集団が苦手な要因が言語の非流暢性であれ、感覚的な過敏さであれ、共通して必要な対策は人数の制限です。
• 個別(1対1)の活動を優先する: 最も推奨されるのは、マンツーマン(個別)での活動です。実際にマンツーマンの療育で成果が出ているのであれば、引き続き個別で対応してくれる場所を中心にしていくのが良いでしょう。
• 少ない人数での活動を工夫する: 現実的に個別対応が難しい場合でも、なるべく人数を絞って活動できるように環境を調整することが望ましいです。人数が少ない環境を作ってあげることが、最も良い方法とされています。
3-2. 活動の見通しを立てて心理的ハードルを下げる
活動そのものに対する心理的なハードルを下げる工夫も有効です。
• 見通しを立てる: 活動の内容や流れについて、ある程度事前に見通しを立ててあげることが大切です。次に何をやるのか、どれくらいの時間で終わるのかが分かると、子どもは安心感を得やすくなります。
4. まとめ:配慮ある環境づくりが最善の支援
集団が苦手な子どもへの支援は、苦手な部分を克服させるための「訓練」ではなく、**本人の特性に合わせた「環境の配慮」**が中心となります。
特に人数を絞る、個別に対応する、活動の見通しを明確にするなど、子どもが心理的に安心して活動できる環境を提供することが、集団への苦手意識を軽減するための最善の方法と言えます。
実際の受け皿としては、オンラインのフリースクール(→詳しくは本校のご案内)もしくはマインクラフト×発達障害のオンライン個別支援をご確認ください。
オンライン活動説明会・所要30分・無料相談はこちら

SUPER SCHOOL
不登校や発達特性のある小中学生向けのオンラインフリースクールです。集団が苦手な子どもを対象に、マンツーマンの個別支援を中心に活動をします。